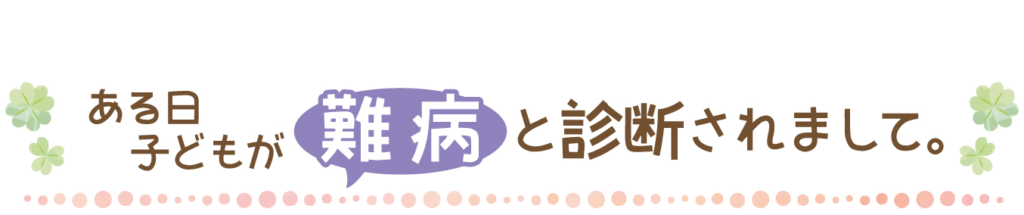
vol.15 発作と薬
2歳3か月の時、突然はじまった娘のてんかん発作。
病気が分かってからすぐ飲み始めた薬のおかげで、一時はほぼゼロになっていた。ただ、完全にはなくなることはなく、増えたり減ったり、強くなったり弱くなったりしながら断続的に発作が続いていた。
てんかんの発作を抑える薬は10種類以上もあり、発作のタイプを見極めながら医師と相談して選択していく。単剤で抑えられない場合は2剤、2剤でだめなら3剤と、副作用の様子を見ながら、少しずつ、少しずつ、増やしたり減らしたりして調整していく。
てんかん患者の7割程度は薬で発作をコントロールできるそうで、残る1~2割も外科的治療(手術)の併用でおさまる場合が多い。次の薬で効くかも、もう少し増やしたら効くかも、と期待しすぎないように期待しながら調整していく。
てんかん発作は脳波に影響があるため、脳の発達を遅らせてしまう。そのため子どものてんかんはとにかく少しでも早く発作をコントロールすることが最重要。脳が急成長する時期に発達が邪魔されてしまうと、後々まで知的な障害が残ってしまう可能性が高い。

薬を飲ませるといっても、病気のことを理解できない2歳児に薬を飲ませるのは簡単ではなかった。
発症から毎日朝晩、ゼリーやジュースでゆるいお団子状にした粉薬を飲ませる。
娘は娘なりに、飲まないといけないものと認識しているのか口に入れられる薬を吐き出したことはほぼなく、健気に「ごっくん」と飲み込む。
素直に口を開けて飲めた日もあったけれど、嫌がる日は私の腕に爪を立てて抵抗する娘に馬乗りになって2人で泣きながら飲ませた。
私には毎日の薬の時間がとてもつらい時間で、健気にがんばって飲み込む娘を抱きしめて、「えらいね、えらいね」と飲むたびに褒める。だから娘も飲むたびに、涙目になりながら「えらいね、えらいね」と自画自賛した。
そうして娘が毎日がんばって薬を飲んでも、発作は減るどころかむしろ増えていった。
効かない薬が恨めしく、飲ませるのを余計につらくさせた。
薬でのコントロールが簡単にはいかないとの判断で、発作時の脳波を調べてもう少し正確に発作タイプなどを見極めるため、検査入院をすることになった…。
てんかんと抗てんかん薬
’てんかん’というと発作を起こして突然倒れたり自動車事故を起こしたりするイメージがあるかもしれませんが、てんかん患者は全国に100万人いるとされ、現れる発作タイプは様々です。
てんかんを発症すると、抗てんかん薬と言われる発作を抑える薬を服用します。10種類以上ある薬を、発作タイプに合わせて調整しながら服用し、それでも抑制(コントロール)できない場合は外科的治療(=手術)を検討します。80-90%人は抗てんかん薬と外科治療で発作を抑制できて問題なく日常生活を送ることができます。残りの10-20%の人が難治性てんかんとなります。
※このコラムは、西広島タイムス紙面に2019年から連載した内容を加筆・修正して掲載しています。
【 コラム作者 】
広島市在住の3児の母。
末娘が2歳のとき「結節性硬化症」という難病と診断される。
子どもの病気や障害と向き合いながら、子育てや仕事に毎日奮闘中。
