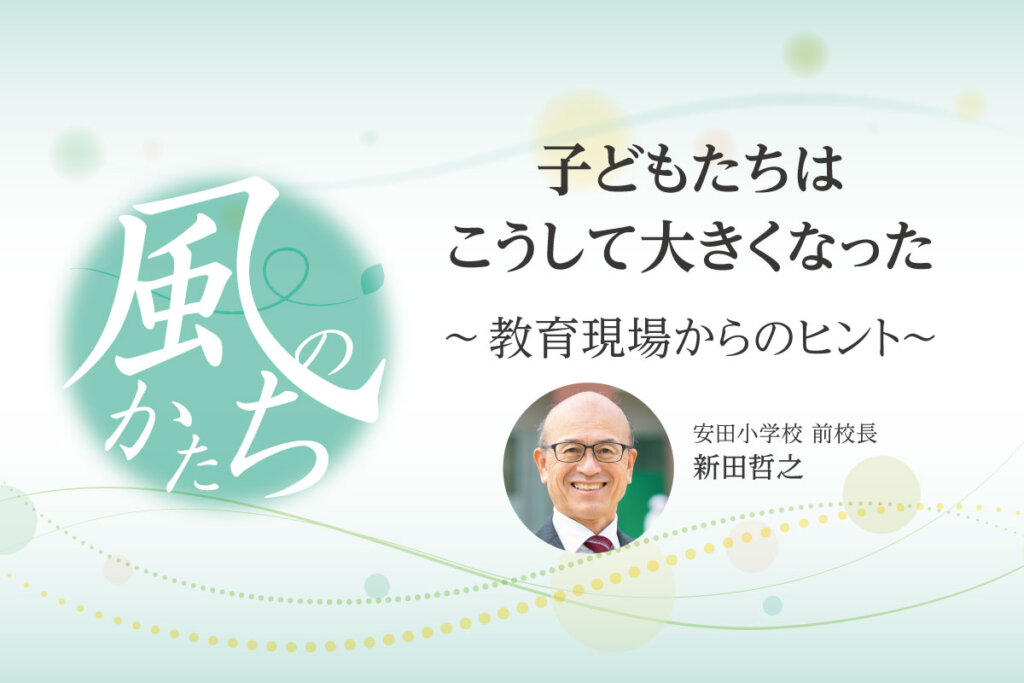
聞く力
話を聞くということは、誰でもできることです。子育てされている方にどんな能力をつけさせたいかと質問したら、聞く力をいちばんにあげる方は少ないように思います。
幼児期や学童期に聞く力は必要だけれど、理解力や表現力、あるいは数学的な思考や科学的思考のような考える力に目が向きます。健康な体を保持する体力も大事ですし、音楽的情操力もつけてほしいと思います。幼稚園でも学校でも多少のことは聞かなくてもやっていける、聞く力がなくても理解する力があれば大丈夫と考えるかもしれません。
聞くということは理解する力のひとつです。小学校の低学年では欠かせない大事な能力です。特に、1年生の入門期の授業では聞く力がないと何もできません。
小学校では教科それぞれに目指す能力があり、主体性や持続力といった態度もありますが、多くの能力と態度に聞く力がつながっていて、お互い影響し合っているのです。
聞く力がなければ思考が働かず、思考力がないと聞くことが十分できず、反対に、聞く力がついていけば様々な能力がついて、良い影響をもたらします。
では、どうやって聞く力をつけるのか?―
学校では授業で系統的につけていきます。1年生の4月は、国語でも算数でも聞く授業をしているように思えるほど、聞いて考え、聞いて活動をします。4月以降も聞く学習は続き、1年生と2年生で話の順序を理解する学習を国語で行い、すべての教科で聞く力を必要とします。
また、日常、教師は目と目を合わせて聞く指導をします。できるようになるまで繰り返します。目が合わない子どもは話を取り違えたり、聞きもらしたりしてしまいます。目を合わせていなかったために聞くことができなくて、困った体験をすることが大事です。
家庭にも協力してもらい、何度も困らせて、何度も練習して、良い習慣をつけていきます。一方で、聞いて良かった体験も大事です。家庭でも学校でも正しく聞いて良かったと、ともに喜べることがあれば、積極的に聞くようになります。
担任をしていた頃、話を聞くことが苦手な子どもがいました。何かの刺激に注意が向く子どもでした。正しく聞けないので友だちとうまく遊ぶこともできず、私の後をくっついて歩くことが遊びでした。
それでも、クラスの仲間といっしょに楽しむ時間がありました。それが、朝と帰る前の読み聞かせの時間でした。読み聞かせの時間になると、子どもたちが私のまわりに集まり本を読む声に耳を傾けます。
しかし、初めはうまくいかず、その子どもはまわりの見えるものが動くと注意がそれるので、誰かが立ち上がってしまうと聞けなくなります。誰かが声を出すとそちらが気になります。それで、特別席をつくり私の膝の上に乗せて読み聞かせをしました。
そのうち、他の子どもが耳を傾けて聞けるようになりました。立ち上がる子どもはいません。音も出さず、本に目を向けています。私の読み声を積極的に聞くようになりました。聞くことが苦手な子どもは、特別席に座る必要がなくなりました。クラスの子どもと私の幸せな時間になりました。
聞くことは、教育の初めの一歩です。聞くことは楽しいと、子どもが感じる学校でありたいと思います。
《コラム「風のかたち」執筆者》
学校法人安田学園 安田小学校 前校長 新田哲之
過去の記事はこちら↓

