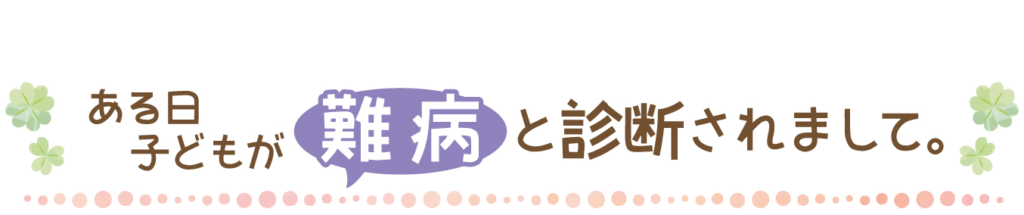
vol.24 大学病院小児科の子どもたち
◇2017年夏
広大病院小児病棟には、色々な病気の子が入院している。聞いたこともない難しい病気や小児がんの子も多く、何カ月も入院していることも少なくない。
副作用で頭がつるつるの子どもたちが廊下で鬼ごっこをしていたり、小さな小さな男の子が慣れた様子で点滴台を押して歩きながら、看護師さんに戦隊ヒーローの話をしていたりして、ちょっとせつなくなる。
うちの長男と同じ小学校高学年くらいの男の子が、病棟の中庭でお母さんとキャッチボールをしているのを見かけた。小児病棟は回廊型になっていて中庭になっている。男の子は医療用キャップをかぶっていて、でも元気そうにキャッチボールをしていた。本当は外で友だちと思いっきり野球をしたいよねと思って、勝手に胸が締め付けられた。

娘は3泊4日の入院で、3種類の脳の画像を撮る検査を受ける。
脳磁図(脳内の磁場を計測)、PET/CT検査(がんの診断などに用いられる検査)、SPECT検査(脳内の神経伝達物質の受容体の分布を評価)の3つで、とにかく脳を詳しく調べて、てんかん発作の震源地を割り出そうというものだった。

入院中は朝から絶食→薬で鎮静→検査という流れで、検査のたびに大量の鎮静剤を使われて入院中ずっとふらふらしていた。娘は鎮静剤が効きやすく切れやすいそうで、鎮静の点滴薬が入ると面白いほど一瞬で眠りに落ち、大きな機械に寝かされて検査していたら急に意識が戻り先生が慌てて鎮静剤を追加することもあった。
検査が終わって部屋に戻ると、足はふらふらでも目はぱっちり。遅いお昼ごはんを「食べる!」と言って元気にパクパク食べた。
※このコラムは、西広島タイムス紙面に2019年から連載した内容を加筆・修正して掲載しています。
【 コラム作者 】
広島市在住の3児の母。
末娘が2歳のとき「結節性硬化症」という難病と診断される。
子どもの病気や障害と向き合いながら、子育てや仕事に毎日奮闘中。
