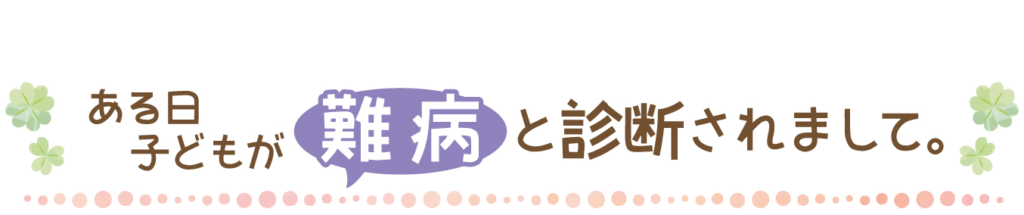
vol.21 てんかん発作との終わりなき戦い
2017年 春
3歳の娘は、保育園の年少児クラスに進級した。
抗てんかん薬を調整して、一旦は少し落ち着いていた娘のてんかん発作。この春頃から発作はまた乱発していて、両腕がピクッピクッと持ちあがる[ミオクロニー発作]というタイプの発作が毎日3~8回程度あった。週に1~3回は、下手すると5分程続く大きい発作も出ていた。
抗てんかん薬は副作用が強いため、少しずつ量を増やしながら調整していく。副作用が強すぎないか、血中濃度が高すぎないか、発作の強さや頻度に変化があるか、確認しながら調整していく。
薬は種類ごとに、成分の血中濃度の目安が決められていて、基準値に達するまで増やしたら、また他の種類の薬を少しずつ増やしていく。
発作を抑える薬はたくさんの種類があるので、1剤ずつ効果を検証していく。1度に摂れるのは4~5剤が限界なので、基準量でも発作が治まらないと、今度はあまり効いてなさそうな薬を選んで少しずつ減量していき、代わりの新しい薬を少しずつ増やしていく。
そうして、月に2回ほど大学病院に通院しながら、娘に合う薬に巡り合えるのを信じて、少しずつ調整していった。
薬の選択に失敗すると発作が増えることもあり、しばらく意識を喪失するような発作が続いたこともあった。1度新しいタイプの発作が出ると薬を元に戻しても治まらず、発作時の脳波を測る入院検査をして新たな薬を調整していく必要があった。

娘に顕著に現れた副作用は眠気だった。
薬を増やすと眠くなってフラフラになり、元気がなくいつも目は半開き。病気を発症するまでいつもにこにこ元気だった娘が、いつもぼーっとして食欲もなく大きな声も出なくなっているのは見ていて辛かった。
保育園の先生から突然連絡が入り、「昏々と眠っていて呼びかけに反応しません」と言われて血の気が引いたこともあった。慌てて大学病院の担当医に連絡を取って連れて行くと、眠りすぎて食事が摂れていなかったことによる低血糖との診断で点滴をしてもらった。
発作が落ち着いても、副作用が強すぎて日常生活が送れなくなったら意味がない。発作と副作用のバランスを取りながら、少しずつ薬の調整を繰り返して、繰り返して、発症から1年を過ぎたころー。
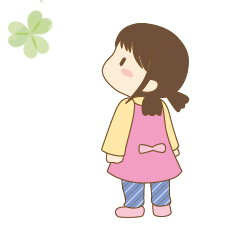
娘は、薬だけで発作をコントロールできない難治性てんかんと判断され、外科的な治療、つまり手術による改善の可能性があるか検討してもらうことになった。
※このコラムは、西広島タイムス紙面に2019年から連載した内容を加筆・修正して掲載しています。
【 コラム作者 】
広島市在住の3児の母。
末娘が2歳のとき「結節性硬化症」という難病と診断される。
子どもの病気や障害と向き合いながら、子育てや仕事に毎日奮闘中。
